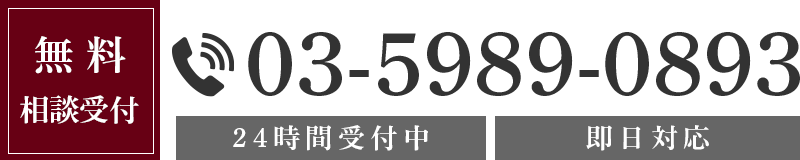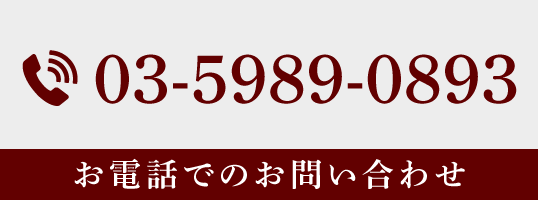【事例】
Aさんは、山口県下関市で飲食業を営む会社であるⅩ社の従業員です。
Ⅹ社では、来年度からインターネットでの通販を利用して自社のレトルト食品を日本全国に販売することを目指しています。
しかし、Ⅹ社は、これまで自社店舗での販売と地元の小売店への販売しかしていませんでした。
そこで、このような事業拡大にともなって生じる課題に対応するために、Ⅹ社では法務部門を新設することになりました。
そして、Aさんが新設される法務部門の責任者となりました。
X社の法務部門では、事業拡大の際に様々な業者と取り交す契約書のチェックも業務となっています。
しかし、Aさんは弁護士資格を有しているわけではありませんし、他の社員も弁護士資格は有していません。
また、X社にはこれまで顧問弁護士もいませんでした。
そこで、Aさんは、今後予想される契約書チェック業務に対応するために、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
このページの目次
1 はじめに
前回の記事では、契約書の押印についてみてきました。
今回は、契約書に押印があるということの法律的な意味について深掘りしていきます。
2 文章の成立の真正
契約が成立して契約書を取り交わし、契約のとおりに契約の内容が完遂できれば問題になることはあまりありません。
しかし、何かトラブルがあった場合に、当事者の間で争いが生じ、契約書どおりに契約が成立したかどうかが問題になることがあります。
そのように争いが生じた結果、民事裁判になったとしましょう。
このような民事裁判で契約書を証拠として提出する場合、「成立が真正であることを証明しなければならない」とされています(民事訴訟法228条1項)。
このように文書が真正に成立したものだと証明する必要が出てくることがあります。
この場面で、“二段の推定”と呼ばれる方法を使って証明することができます。
この二段の推定の場面で、契約書の押印が重要な意味を持ってきます。
3 二段の推定
まず、民事訴訟法228条4項には、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」という規定があります。
そして、この「本人又はその代理人の署名又は押印があるとき」というのは、この「署名又は押印」が「本人又はその代理人」の意思に基づいてされたといえる必要があります。
つまり、「本人又はその代理人」の意思に基づいてされた押印があれば、この民事訴訟法228条4項に基づいて、文書が真正に成立したものと推定されます。
これは二段の推定のうちの二段目の推定です。
そこで次に問題となるのは、その押印が「本人又はその代理人」の意思に基づいてされたのかどうかです。
しかし、日本の社会においては、印鑑は大切に保管するものですから、本人の印鑑を他人が勝手に使用するなどということは、通常はありえません。
そのため、反証がない限り、本人の印鑑で押印されていれば、それは本人の意思に基づいて押印されたのだと推定できるというのが判例の考えです。
これが一段目の推定です。
以上から、本人の印鑑による押印があれば、それは本人の意思に基づいた押印だと推定され、そのことと民事訴訟法228条4項により、文書全体が真正に成立したものだと推定されることになります。
ところで,なぜこのような規定が置かれているのでしょう。
文書が真正に成立したものだと証明するのは必ずしも容易ではありません。
嘘をついてでも裁判に勝ちたいと考える者は「その契約書にサインをしたのは自分ではない」と平気で主張することがあるからです。
しかし、契約書に相手の署名や押印がされているのに、それだけでは真正に成立したのだといえないのでは違和感があるのではないでしょうか。
その問題を解決するのがこの二段の推定なのです。
今回は、契約書に押印があることの持つ意味、特に二段の推定について解説していきました。この続きは今後の記事で解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関わってきた経験を活かし、そもそも会社内でのトラブルを回避するための対応・アドバイスにも力を入れています。
契約書の確認をしてほしい、継続的に弁護士からアドバイスを受けたいなどといったご要望の方も、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。