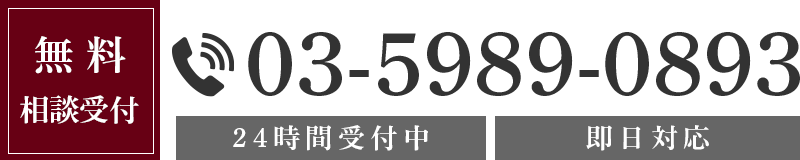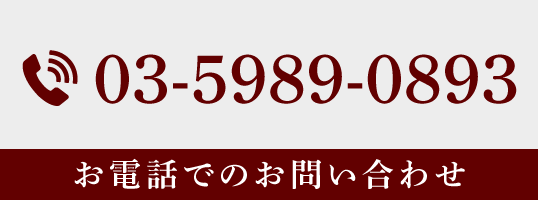企業内あるいは外部との取引において、水増し請求をしたり不正経理をしたりして、横領等を隠蔽したり、差額分を着服したり相手方からキックバックを受けたりすることがあります。このような不正行為は長期間にわたって続けられることが多く、被害は甚大になることが多々あります。
不正経理行為に対して成立する犯罪や、その予防について解説します。
このページの目次
詐欺・電子計算機使用詐欺
実際に行ってもいない出張の交通費を会社に請求したりすることなどが考えられます。このような行為は詐欺罪に当たり、10年以下の懲役に処されます(刑法第246条第1項)。
虚偽の費用や給与金額を入力して給与振り込みをさせるなど、自然人の担当者に虚偽の情報を伝えるのではなく、虚偽の情報をコンピューターに入力して利益を得た場合、電子計算機使用詐欺罪が成立します。法定刑は詐欺罪と同じ、10年以下の懲役です(刑法第246条の2)。
業務上横領・窃盗
会社内の備品を勝手に売却したりすることが考えられます。自分が管理担当者であるなど、業務上自己の支配下に置いているといえる場合は業務上横領罪(刑法第253条)、そうでない場合は窃盗罪が成立します(刑法第235条)。
背任罪
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第247条)。知り合いに便宜を図るため、通常であれば融資しないような案件で融資を行うような場合が考えられます。
取締役等が行えば、特別背任罪が成立し、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、又はこれを併科される(会社法第960条)という、非常に重い刑を科されます。
前述の業務上横領罪等に該当すれば、より重いこれらの罪の刑が成立します。背任罪とこれらの犯罪のいずれが成立するかは、具体的な事案により判断されますが、犯罪の種類ごとに判断はある程度類型化されています。例えば、業務上横領罪か背任罪かについては、自己の名義・計算で行えば業務上横領罪、本人つまり会社の名義・計算で行えば背任罪となるとされています。
第三者への対応
水増し請求など第三者がかかわる場合、自社は他社にとって加害者となりえます。取引先に水増し請求をして実際に行った業務より多くの代金を支払わせた場合、取引先を被害者とする詐欺罪に当たります。これに続いて、自社には実際に行った業務分の代金が支払われたと報告して、差額分を着服することが考えられます。このようなことをすれば自社に対する業務上横領が成立します。また、取引先で不正を行った者について成立する犯罪の共犯(刑法第60条以下)となる可能性もあります。
社内調査
以上のような不正行為は、他にチェックする人がいなかったり、複数名がチェックすることになっていても形骸化している状況を利用して行われます。その結果、誰も気が付くことなく、長期間にわたって続けられることが多いです。メンバーの異動があっても、「今までこういう風にやってきたから」などと言われて、特に疑問に思うことなく受け入れてしまい、不正が行われ続けてしまうことも多く見受けられます。
このような不正が発覚したとしても、既に長期間行われていて、被害金額が膨大になっている可能性があります。また、時間の経過により、資料も散逸していて、被害金額を特定することが困難なこともあります。
責任追及
不法な行為によって自社が損害を受けた場合、損害賠償を請求できます(民法第709条)。
取締役や監査役等の役員等に当たる者が、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによった損害を賠償する責任を負います(会社法第423条第1項)。第三者に対し賠償責任を負う場合もあります。
基本的には、不法行為をした者自身が当該第三者に損害賠償責任を負います。役員等であれば、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法第429条第1項)。第三者の損害についての故意ではなく、職務上の注意義務ついて悪意又は重過失があれば該当します。
また、従業員などの被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、企業も、その損害を賠償する責任を負います(民法第715条第1項)。
時効
被害金額を特定できたとしても、不正が長期間行われていた場合、初期に行われた不正行為については、時効にかかっている可能性があります。
民事責任については、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者側が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効により消滅します(民法第724条)。
取締役の任務懈怠責任等不法行為以外の責任の場合は、他の債権と同じく債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効により消滅します(民法第166条第1項)。
刑事責任については、刑の種類により時効の期間が異なります(刑事訴訟法第250条)。電子計算機使用詐欺罪や業務上横領罪の場合は、10年以下の懲役ですので、7年経過すれば、時効により消滅します(刑事訴訟法第250条第2項第4号)。時効より前の不正行為については、刑事処分を求められなくなります。
不正防止のために
以上のように、不正経理が行われれば、自社に多大な損失をもたらすだけでなく、自社が加害者となり、責任を負うことになりかねません。
このような事態を防ぐために、企業内におけるコンプライアンス体制を整備しておく必要があります。
内部通報制度を整備するなどして、不正の報告をするハードルを下げることなども重要です。
企業犯罪の防止についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。