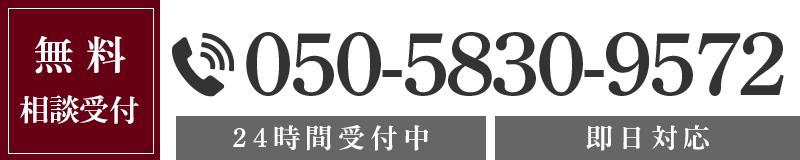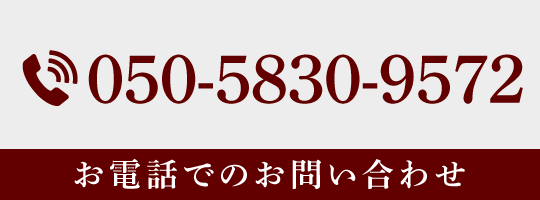Archive for the ‘企業犯罪’ Category
企業経営と司法取引③

前回までの記事では司法取引の概要やその流れについて解説させていただきました。
今回の記事ではその内容を前提にして、会社の経営者や法務担当者としてどのような点に留意すべきかについて解説させていただきます。
司法取引,刑事免責についての解説はこちら
1 外部に機密情報が漏えいするリスク
司法取引の導入は、事件情報を提供した者に自身の刑事処罰の軽減というインセンティブを与えることになります。
そのことによって、仮に自社が関与した刑事事件について、捜査対象となった社員が捜査機関に対し、会社よりも先に情報を提供する場合が多くなることを想定する必要があります。
当然事実の隠蔽はしてはいけませんが、捜査機関より先に会社内で事情を把握することは問題が大きくなることを防ぐために重要です。
そこで、今後はより一層自社内で不正や、違法行為を早期に探知することが重要になります。そのためには自社内の情報の提供体制や、不正がないかを確認する監査体制を強化することが求められているといえます。
2 当時者との利益相反のおそれ
会社内での不正が問題となる場合、会社の社員と経営者、会社自体との間では利益相反可能性が生じるおそれがあります。
利益相反というのは、当事者の一方が有利に働く場合に、もう一方が不利になる関係をいいます。
司法取引制度が導入されている現状においては、下記のような利益相反の事態が発生しる場合があります。
【事例】
X社の社長Aは部下であるBに指示して虚偽のに用を含む申請者を作成させY県から補助金を騙し取った。
(事例はフィクションです)
この場合において、Bさんが捜査機関からX社の不正を暴くために司法取引を持ち掛けられた場合に、Bさんは司法取引に応じることで自身の刑罰が軽くなるという利益を得られるのに対して、AさんやX社はBさんの証言により詐欺罪に関与されたことが裏付けられるので不利になります。
このようなBさんと、Aさん、X社との関係のことを利益相反関係といいます。
司法取引が導入されたことにより、以上のような自社の社員と上司、社員と経営者や会社自体との間で利益相反状態になることが想定されます。
利益相反状態になった場合には、双方の弁護人を1人の弁護士が担当することはできませんので、信頼できる外部の弁護士に相談できる体制を整えておくことは重要になります。
3 司法取引制度が導入されたことを前提にした平時の対応について
平時の対応としては、まず司法取引制度について企業の経営者や法務担当者が正しく理解をして、どのような事態が問題なるかについて共有しておくことが必要です。
その上で1、2で述べたようにこれまで以上にしっかりとした不正防止の監査体制や内部通報システムの構築や、不祥事対応に精通した弁護士との連携が求められます。
弊所ではこれまで刑事事件を中心に扱ってきましたので司法取引や、それに伴う刑事事件対応には精通しています。
また弁護士をはじめとする専門スタッフが平時の相談やセミナー、監査体制の構築や不祥事対応についてお手伝いさせていただく、顧問契約も準備しております。
初回の相談は無料ですので、司法取引制度に関してご不安やご相談があるかたはまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
企業における営業秘密の情報漏洩④

企業において営業秘密の情報漏洩があった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前回までは、不正競争防止法上の保護を受ける「営業秘密」といえるためには、どのような要件を満たす必要があるか解説しました。
今回は、同法上の保護を受ける営業秘密が実際に存在し、同営業秘密の情報漏洩があった場合の罰則について解説します。
営業秘密侵害罪とは
営業秘密侵害罪は、比較的新しく作られた犯罪であり、平成15年の不正競争防止法の改正によって導入されました。
それ以前には、企業において保有している情報を企業外に持ち出す行為については、刑法による処罰が行われていました。
例えば、企業内部者が、紙に記載された営業秘密資料を密かに持ち出して企業外の第三者に手渡し、その第三者がコピーをとって直ちに企業内部者に返却したとしても、裁判所は、持ち出したファイルという紙媒体の価値だけではなく、紙媒体に化体した情報の価値に着目して窃盗罪を認めていました。
しかし、現在においては、紙媒体を持ち出さなくても情報の企業外への持ち出しが可能であり、情報をメールで送ることも可能ですし、USBメモリにコピーしたりすることもできます。このような場合、窃盗罪は、財物に対する犯罪ですから処罰できないことになってしまいます。そこで、このような場合でも処罰を可能にするべく営業秘密侵害罪が創設されることになったのです。
営業秘密侵害罪の主観的要件
営業秘密侵害罪が成立するためには、行為者について、「不正の利益を得る目的」または「営業秘密保有者に損害を加える目的」があったことが必要とされています(これは、一般的に図利加害目的といいます。)。この図利加害目的を要件とすることで、内部告発、研究目的、報道目的等での営業秘密の利用は除かれることになります。
営業秘密の侵害行為とは
詐欺や窃盗等の不正の手段によって営業秘密を取得する行為(不正競争防止法21条1項1号)や詐欺や窃盗等の不正の手段により取得した営業秘密を使用または開示する行為(同法21条1項2号)などが営業秘密を侵害する行為とされています。
そして、営業秘密侵害罪が成立するとなった場合には、その刑罰は相当に重く、法定刑は、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金、またはこれを併科すると規定されています。
また、こうした営業秘密を侵害する行為の一部については、法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、その行為を行ったときは、法人も罰金(法定刑は5億円以下。同法22条1項2号)の対象とされています。
たとえば、A社の代表取締役Xさんが、A社の事業に利用するため、競合会社B社の従業員Yさんを騙し、「営業秘密」が入ったUSBメモリを取得した場合、Xさんだけではなく、A社も刑事責任を問われることが考えられます。
次回は、営業秘密保護のための管理体制の構築について解説します。
社内の情報保護規定,体制の構築について関心のある方は,弊所では無料相談も実施しております。お気兼ねなくお問い合わせください。
民泊サービスを始めるための注意点②
民泊サービスを始める場合の法律上の注意点に関し弁護士が解説します②
【事例】
Aさんは京都市内で不動産業を営んでいるX社の代表取締役を務めていました。
Aさんは近年京都市内を訪れる観光客が増えていることに目を付けて、自社が保有する空き物件を活用し民泊事業を開始しようと考えました。
しかし、Aさんは民泊業を行うためにどのような設備や手続が必要か分かりませんでしたので民泊サービスの許認可関係に強い弁護士に法律相談をしました。
(事例はフィクションです)
前回の記事では民泊業を行う場合に旅館業法上の営業形態について解説しました。
今回の記事では旅館業法上の許可が必要になる場合はどのような場合であるかについて解説をさせていただきます。
1 旅館業法の許可が必要な場合について
旅館業法では旅館業を営業する場合には、旅館業法に基づく営業許可を受けなければならないと定められています。では旅館業を営業するとはどのようなものを指すのでしょうか。
旅館業法では旅館業について「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
この定義は①宿泊料を受けて、②宿泊させる、③営業の3つの要素に分ける事ができます。
3つの要素について順に解説させていただきます。
①「宿泊料」について
宿泊料を受けているかについて料金の名目は問わず、寝具や部屋の使用料とみなされるかを実質的に判断されます。
例えば古民家などで「日本文化の体験費用」という名目で費用を払ってもらっていたとしても、実質的にはその古民家に泊まらせており寝食の代金として徴収していることが明らかな場合には宿泊料を受けているとみなされます。
②「宿泊」について
宿泊とは寝具を使用して施設を利用することとされています。
つまりベッドや布団などを用いて泊まらせる場合には、宿泊させる場合に該当するといえます。
③「営業」について
営業とは、「不特定多数の人」を対象に「反復継続」して事業として行なうこととされています。
例えば、ネットで繰り返し不特定多数を集客して有料で部屋を貸すような場合は営業にあたります。
民泊によくあるような海外のサイトと連携して集客をする場合もこれに該当します。
反対に友達に対して何日か部屋を貸すような場合には、仮にお金を貰っていたとしても特定の者を対象としており、反復することも予定されていないので「営業」には該当せず特段の許可は不要です。
Aさんは、自社の物件を使用して利用者に宿泊料を払ってもらって継続的に民泊を営むことを計画していると思われますので、原則として旅館業法上の許可が必要になると思われます。
2 許可をせずに営業をした場合にはどうなるのか
では旅館業法の許可が必要なAさんのケースのような場合に許可をせずに営業を行った場合にはどうなるのでしょうか。
旅館業法10条には次のような定めがあります。
旅館業法第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
条文の通り無許可営業には「6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金」という刑事罰が定められています。
実際に無許可で旅館業を営んだことで逮捕され報道されてしまったケースもあります。
社名や会社代表の実名が報道されてしまえば、社会からの信頼を失い経営基盤が大きく揺らいでしまいます。
無許可営業を知らずに行ってしまうことがないように、これから行おうとする民泊サービスには許可が必要かどうかについて、許認可関係に詳しい弁護士に是非一度ご相談ください。
施術所の開設手続き②

【事例】
Aさんは、一念発起して、自宅のある奈良県天理市内で、資格を取得して鍼灸整骨院を開業しようと考えました。
Aさんは、鍼灸整骨院を開業するのには資格がいるというのは分かっていましたし、資格取得のために通い始めた学校も卒業が近付いてきました。
また、患者として鍼灸整骨院に通っていた経験から、健康保険も使える場面もあるようだということも知っていました。
しかし、具体的にどのような手続きをする必要があるのかまでは分かっていませんでした。
そこで、Aさんは、今後必要な手続きなどを相談するために、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、鍼灸整骨院を開業するにあたって、必要となる準備について解説してきました。
そして、必要となる資格、具体的には、柔道整復師、はり師、きゅう師の資格について解説してきました。
今回は資格取得後に必要となる届出についてみていきます。
2 必要となる届出
前回の記事でも解説しましたが、柔道整復師については柔道整復師法が、はり師やきゅう師についてはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下では、各資格の頭文字をとって「あはき法」といいます。)が、業務に関する規律も規定しています。
まず、柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所のことを施術所といい(柔道整復師法2条2項)、はり師やきゅう師についても、業務を行う場所のことを施術所と呼ぶことを前提に規定がされています(あはき法9条の2第1項等)。
この施術所を開設した場合、開設してから10日以内に、施術所の所在地の保健所に届出をする必要があります(柔道整復師法19条1項前段、あはき法9条の2第1項前段)。
この届出の際に必要となるのは、柔道整復師の場合、業務に従事する柔道整復師の氏名(柔道整復師法19条1項前段、同法施行規則17条5号)、施術所の場所(柔道整復師法19条1項前段、同法施行規則17条4号)のほか、開設者の氏名と住所、開設年月日、施術所の名称、施術所の構造設備の概要と平面図(柔道整復師法19条1項前段、同法施行規則17条1号から3号、6号)が必要となります。
はり師やきゅう師の場合、基本的には柔道整復師と同じような内容が必要となるほか(あはき法9条の2第1項前段、同法施行規則22条1号から4号、7号)、開業するのがはり師なのかきゅう師なのかといった業務の種類(あはき法施行規則22条5号)、業務に従事する施術者の目が見えない場合はその旨(同施行規則22条6号)が必要となります。
また、こういった届出事項に変更が生じた場合にも、10日以内に、施術所の所在地の保健所に届出をする必要があります(柔道整復師法19条1項後段、あはき法9条の2第1項後段)。
更には、施術所を休止や廃止にしたとき(柔道整復師法19条2項前段、あはき法9条の2第2項前段)、休止した施術所を再開するとき(柔道整復師法19条2項後段、あはき法9条の2第2項後段)も同様に10日以内の届出が必要となります。
3 構造設備に関する規律
施術所は、どのような場所でも開けるわけではありません。
構造設備に関する基準や衛生上必要な措置に関する基準も定められています(柔道整復師法20条、あはき法9条の5)。
今回は、柔道整復師やはり師、きゅう師として施術所を開設するのに必要な届出について解説していきました。この続きは今後の記事で解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関わってきた経験を活かし、そもそも法律に違反しないための対応・アドバイスにも力を入れています。
許認可申請についてアドバイスがほしい、継続的に弁護士からアドバイスを受けたいなどといったご要望の方も、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
企業における営業秘密の情報漏洩②

企業において営業秘密の情報漏洩があった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けるためには
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法2条6項)。
すなわち、同法上の営業秘密は次の3つの要件を満たす必要があります。
- 秘密として管理されている情報であること
- 有用な情報であること
- 公然と知られていない情報であること
の3要件です。
今回は、この中で、比較的問題になることが少ない②有用性と③非公知性の要件について解説します。
有用性の要件について
有用性の要件について、経済産業省が出している「営業秘密管理指針」には、「有用性」が認められるためには、その情報が客観的にみて、事業活動にとって有用であることが必要である。その一方、企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する内容の情報は、「有用性」が認められないとされています。
「有用性」の要件は、公序良俗に反する内容の情報(脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報)など、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密から除外した上で、広い意味で商業的価値が認められる情報を保護することに主眼があります。したがって、秘密管理性、非公知性の要件を満たしている情報は、有用性が認められることが通常であり、また、現に事業活動に使用・利用されていることを要するものでもありません。過去に失敗した研究データや、製品の欠陥情報等のいわゆるネガティブ・インフォメーションにも有用性は認められます。
非公知性の要件について
同じく経済産業省が出している「営業秘密管理指針」によると、「非公知性」が認められるためには、公然と知られていない状態であることが必要であり、同状態とは、当該営業秘密が一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態であるとされています。具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態のことです。
この点、当該情報が実は外国の刊行物に過去に記載されていたような状況であっても、当該情報の管理地においてその事実が知られておらず、その取得に時間的・資金的に相当のコストを要する場合には、非公知性はなお認められます。要するに、通常合理的な努力の範囲内では当該情報が入手できない状態を意味するといえます。
参考となる裁判例として、仮にリバースエンジニアリングによって営業秘密である技術情報に近い情報を得ようとすれば、専門家により、多額の費用をかけ、長期間にわたって分析することが必要であるものと推認されることを理由に、非公知性を肯定した大阪高判平成15年2月27日があります。
次回は、最も問題のなることの多い①秘密管理性の要件について解説していきます。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
【事例紹介】風俗営業法違反での行政処分を放置していた結果逮捕された事例②

【事例】
東京・歌舞伎町のコンセプトカフェで未成年の従業員に接待させたとして、警視庁は、店の経営者の男Aと店長の女Bの両容疑者を風営法違反(無許可営業)などで逮捕し、26日に発表した。
いずれも容疑を認めているという。
少年育成課によると、両容疑者は共謀して(中略)コンセプトカフェXで、未成年の少女(17)を女性従業員として雇ったうえ、都公安委員会から風俗営業の許可を得ずに、客の30代男性に酒をついだり、話し相手をしたりするなどの接待をさせた疑いがある。
男は、この女性従業員が未成年と知りながら雇っていたといい、「店で未成年を5~6人ほど雇っていた」と供述しているという。
店は(中略)、これまでも無許可の接待行為について行政指導を受けていた。
(朝日新聞DIGITAL 令和6年9月26日「歌舞伎町のコンカフェで無許可接待、従業員に未成年も 警視庁が摘発」より一部抜粋)
前回の記事では風営法違反の規制内容について解説させていただきました。
今回の記事では、紹介した事例のように風営法違反が明らかになった場合の手続きの流れや、風営法違反による行政指導を無視した場合について詳しく解説させていただきます。
参考記事 風営法の違反とは:弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
1 風営法違反が明らかになった場合の手続き
風営法違反が明らかになった場合には、行政上の手続きと刑事上の手続きの2つが考えられます。
風営法違反における処分には「刑事処分」と「行政処分」の2つがありますが、令和4年での処分状況をみると、刑事処分に該当する検挙件数は874件、一方の行政処分の件数は3,820件と、圧倒的に行政処分の方が多くなっています。
このように風営法違反が明らかになっても直ちに、刑事処分を受けるわけではなく、行政上の手続きを経る可能性の方が高いといえます。
行政上の手続きについて簡単に説明すると、「行政処分」は、行政庁(公安委員会)が適正な営業をするよう指示監督するための処分行為です。
違反行為が発覚したときに報告徴収、立入検査を行い、行為の悪質性を考慮した上で行政指導または行政処分を行います。
立入検査には警察が行う捜索とは異なり強制力はありません。ただしこれを拒否すれば刑事処分に移行する可能性も、拒否しないことが得策と言えます。
ですので風営法違反の発覚後の端緒としては内容の悪質性にもよりますが、まず検査に関する立入検査の通知が来ることからが多いように思います。
行政指導と行政処分の違いは「行政処分」とは、法律の定めに従い、一方的な判断に基づいて、国民の権利や義務に直接影響を及ぼす行為のことをいいます。
それに対して行政指導は、一方的に強制するものではなく「このようにしてください」というようなお願いベースのものになります。
本件事例における行政指導は「これまでも無許可の接待行為について行政指導を受けていた」という報道の内容から、調査などから無許可の風俗営業が明らかになり
「風俗営業にあたるのでちゃんと許可取ってくださいね」
といった内容の行政指導を受けていたのではないかと推測されます。
風営法違反をした場合の行政処分には、軽いものから順に「許可の取り消し」「営業停止」「指示処分」の3つの処分があります。
多くのケースは「指示処分」に該当しますが、その処分内容に従わない場合には「許可の取り消し」「営業停止」といった重い処分が科されることになります。
2 行政指導に従わないとどうなるのか
先ほど説明したように、風営法違反が明らかになっても余ほど悪質なケースを除けば最初は行政指導を受けるにとどまることが多いです。
しかしながらそれに従わないでいれば、営業に影響の出る行政処分を受けたり、刑事処分に移行したりすることになります。
最悪の場合、事例のように経営者が逮捕されることになります。
行政処分を受けた場合や、逮捕された場合には公表や報道により社名や店舗名が明らかになり、社会的信用を失うことになります。
経営者が身体拘束を受けることで経営の継続が困難になる場合もあります。
これらの不利益は事後的に回復することが容易ではありません。
当然違法行為をしないことが大前提ですがもしも違法行為を指摘され行政指導を受けた場合には、違法な状態を改善するために早期の対応をとる必要があります。
行政指導への対応は、まず事実関係を正確に判断した上で対応が必要であれば早期に適切な対応をとることが重要です。
専門家である弁護士に早期に相談されることをおすすめします。
あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで多くの刑事事件を扱ってきた経験やノウハウを生かして、刑事事件になる前段階である行政指導の段階から問題解決に向けてサポートをさせていただきます。
行政指導や行政による調査が行われてお困りの経営者の方は是非一度ご相談ください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
「営業秘密」の裁判例解説②
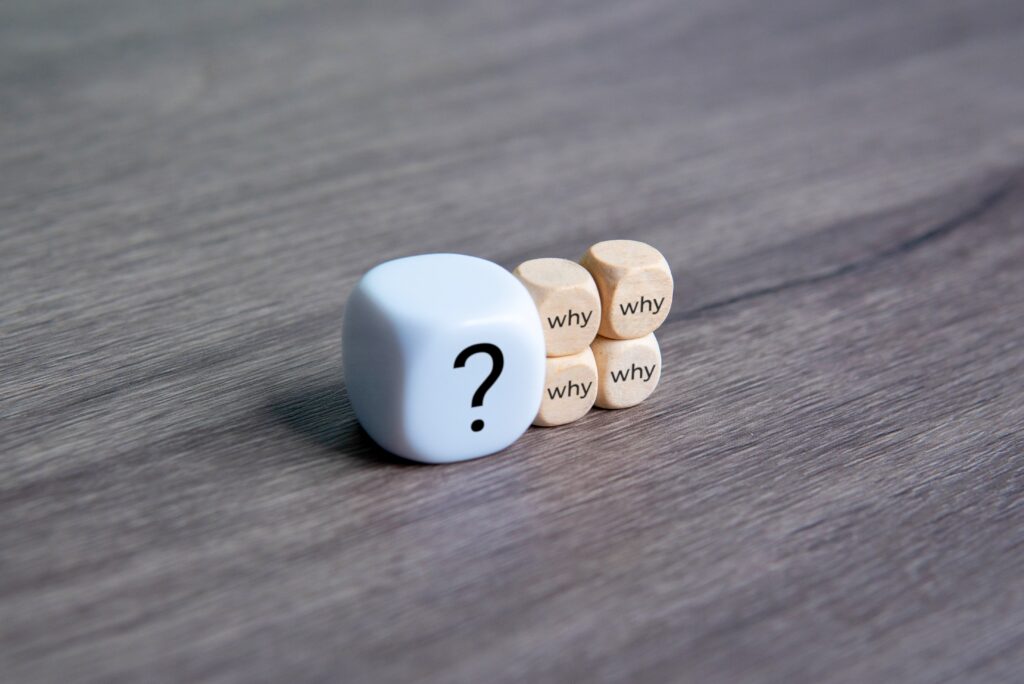
本記事では、横浜地裁平成26年(わ)1529号平成28年10月31日判決について解説します。この判決については、控訴上告されていますが、有罪無罪の結論自体に変更はありません。
本件は、被告人が不正競争防止法で禁止されている営業秘密の領得を犯したものとして起訴されたものの、一部について有罪、一部について無罪となった事件です。このような結論が出ている判決をよく読むと、なぜ一部については有罪になるのに他は無罪となるのかが解ります。それが解ると、営業秘密を守るためには企業がどうするべきなのかも解ります。
本件を簡単にいうと、自動車会社A社で働いていた被告人は、サーバーコンピューターに保存された営業秘密データを複製して持ち出したというデータ領得行為と営業秘密が含まれた教本を持ち出した複製して持ち出したという教本領得行為で起訴されました。
データ領得行為については、営業秘密であるデータを不正の目的で持ち出したものだと認定されて有罪となっています。一方、教本領得行為については、秘密として管理されていたとはいえないとして無罪となりました。
では、なぜデータは営業秘密なのに、教本は営業秘密と認められなかったのでしょうか?
前回の記事では、データ領得行為について有罪となった過程について説明しました。その記事は以下のリンクから確認できます。
今回は、教本領得行為が無罪となった理由を確認します。
結論からいうと、領得された教本が営業秘密に該当するとはいえないという理由から無罪となりました。
では、なぜ営業秘密と認定されなかったのでしょうか。確認していきます。
(1)裁判所の認定によると、教本は次のような管理の仕方で保管されていました。
・教本は、閲覧コーナーに、他の本と共に、表紙の全部又は一部が見えるように展示されていた。
・閲覧コーナーには監視員はおらず、周囲に監視をすることが可能な職員もいなかった。
・教本を紐や鎖でオープンラックとつなげるような措置もなく、閲覧するために氏名等を記載するなどの手続もなく、館内に入った人は誰でも自由に手に取って閲覧することができ、メモをすることも禁止されていなかった。
・教本は若手従業員の育成講座のテキストとして使用され、受講者には終了後に教本が配布され、持ち帰りも許されていた。
(2)本件教本には、社外秘であることを表す文字のスタンプが押されていた。
(3)(1)の事情を踏まえると、(2)があっても営業秘密として合理的な方法で管理されていたとはいえない。
以上の理由から、教本についてはそもそも営業秘密と認めるだけの管理がされていないことから営業秘密として認められなかったのです。
データ領得行為と教本領得行為とで結論が異なった理由から、営業秘密として保護を得るための管理体制について一定の方向性を考えることができます。
まず当然のことながら、社外秘であることを示すマークなりスタンプなりは最低限必要なのでしょうが、それだけで営業秘密と取り扱ってもらえるわけではないようです。
誰がそれを見てよいのか明確に示すこと、誰が確認したのか記録を残すことができるようにすること、他の秘密でないものと適切に分けて管理すること、こういった事情が必要になってくるといえます。
具体的な事件や営業秘密の保護・整理について担当部門の方はこちらからお問い合わせください。
取締役等に対する贈賄罪、収賄罪について

取締役等に対する贈賄罪、収賄罪で自社の取締役が金銭を受け取っていた際の対応を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考報道:東京女子医大を家宅捜索 特別背任容疑、同窓会が実態ない職員に給与
【事例】
A社の取締役であるXさんは、下請け業者のB社のYさんから、自分を優遇してもらうことをお願いされて100万円の金銭を受け取りました。
そしてXさんはYさんが自宅を購入するための資金に困った際に、A社名義でYさんにとって非常に有利な条件で多額の融資をしていました。
以前の記事では取締役が職務に関し金銭を受け取った場合に成立する罪や、成立する要件について解説しました。
今回の記事では、事例のようなケースが発覚した場合の対応について解説します。
1 事実の調査について
事例のようなケースが発覚するのは、事情を知った者からの内部または外部通報によることが多いと思われます。
そのような通報があった場合はまずは当事者に事情を確認して、事実関係を詳細にかつ正確に把握することが重要になります。
以前の記事で解説したように、会社役員の収賄罪については、公務員の収賄罪とは要件が一部異なります。
受け取った金銭が何か職務上の請託を受けてされたものなのか、受け取った利益に関する証拠があるのかなど、当事者の証言や客観的証拠を踏まえて会社法に違反するような事実があるのかについて確認をする必要があります。
会社法に違反するのは以前の記事で説明した収賄だけではありません。
本件事例においては、Yさんに対してXさんが不正な融資を行ったことについて特別背任にあたる可能性があります。
特別背任については会社法960条に規定があります。
会社法第960条
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
四 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六 支配人
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役
明らかに会社の損害にあたるような不正融資(例:返済原資のないものへの無担保での貸し付け)については、事前に金銭の収受などがなくとも特別背任にあたり刑事責任を負う可能性があります。
収賄という形で通報があったとしても、特別背任などほかの罪に当たる可能性はないかなど多角的な視点で調査することが重要になります。
そのような調査を行うためには、法的知識に詳しいものも含めた調査チームを作ることが重要になります。
2 当事者への責任追及
仮に会社法違反であることが明らかになった場合には当事者に対しての責任追及について考える必要があります。
収賄や特別背任については刑罰が予定されているので警察に届け出ることが適当かとは思いますが問題は単純ではありません。
事件の内容的に会社の評判や株主の利益にも関わる事態なのでどのように対処するかは様々な視点から考える必要があります。
会社法にも会社から取締役への責任追及(例:取締役の解任請求)や、株主から取締役への責任追及(例:損害賠償請求)など様々な規定が置かれていますので会社としても当該事例にや会社の置かれている状況などに応じて適切な対処をする必要があります。
対処方法の選択や対処の進め方についても専門家である弁護士に相談しながら進めることをおすすめします
3 再発防止策の策定
事件の処理が終了したとしても、今後事例のような事態が発生しないように再発防止策を策定することは、会社の信頼回復や今後の会社経営において重要な課題になります。
内部通報制度の充実や、取締役等の会社役員のコンプライアンス体制の確立などを検討する必要があります。
不祥事対応,企業犯罪についてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。お問い合わせはこちらからどうぞ。
「営業秘密」の裁判例解説

本記事では、横浜地裁平成26年(わ)1529号平成28年10月31日判決について解説します。この判決については、控訴上告されていますが、有罪無罪の結論自体に変更はありません。
本件は、被告人が不正競争防止法で禁止されている営業秘密の領得を犯したものとして起訴されたものの、一部について有罪、一部について無罪となった事件です。このような結論が出ている判決をよく読むと、なぜ一部については有罪になるのに他は無罪となるのかが解ります。それが解ると、営業秘密を守るためには企業がどうするべきなのかも解ります。
参考報道 「ギャラ」「NG」芸能人の営業秘密持ち出し疑い 会社員の男を逮捕 朝日新聞
本件を簡単にいうと、自動車会社A社で働いていた被告人は、サーバーコンピューターに保存された営業秘密データを複製して持ち出したというデータ領得行為と,営業秘密が含まれた教本を複製して持ち出したという教本領得行為で起訴されました。
データ領得行為については、営業秘密であるデータを不正の目的で持ち出したものだと認定されて有罪となっています。一方、教本領得行為については、秘密として管理されていたとはいえないとして無罪となりました。
では、なぜデータは営業秘密なのに、教本は営業秘密と認められなかったのでしょうか?
データが営業秘密と認定された根拠
判決文「第3 本件各データファイルの営業秘密該当性及びその点に関する被告人の認識について」に詳しい説明がありますので、裁判所が根拠として挙げた事項を確認します。
- データファイルの内容が会社の事業活動にとって有用であったこと。例えば、未発表の製品の仕様が入力されていたり、独自に開発された販売台数を予測するためのシステムツールの使用マニュアルなどが含まれていたようです。
- データファイルに秘匿性が認められること。(1)のデータの有用性を踏まえると、これらデータが漏出した場合、会社の競争力等に影響が生じることから、秘匿性も認められています。
- データファイルへのアクセス制限が行われていたこと。例えば会社の中でも業務に必要なものにしかアクセスすることができないようになっていたことや従業員に対する指導が行われていたことなどが挙げられています。
- 弁護人は、営業秘密と解るようなラベリングがされていないものがあることや宴会の写真など明らかに営業秘密と関係のないものもデータファイルに入っていたことを指摘して、営業秘密該当性を争いましたが、(1)~(3)の状況を踏まえると、必ずしも管理が徹底されていない部分もあったが、営業秘密該当性が否定されることはありませんでした。
以上が、今回の判決のうち、データ領得行為が有罪となった簡単な理由です。
次回、教本領得行為が無罪となった理由を説明しますので、次の記事をご覧ください。
具体的な事件や営業秘密の保護・整理について担当部門の方はこちらからお問い合わせください。
外国人の不法就労について

外国人が適正に就労できるよう、外国人の雇用についても厳格な規制が設けられています。就労資格のない外国人を日本の企業が雇用した場合、その外国人だけでなく雇用した個人や企業も処罰を受けます。ここでは、外国人を不法就労した場合の処罰について解説します。
外国人の不法就労活動
本邦に在留する外国人は、その在留資格により認められた活動や許可の範囲を越えて活動することはできません(出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条第1項)。
別表第一の一、第一の二、第一の五
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー等)
その在留資格に定められた範囲でのみ就労が可能(入管法第19条第1項第1号)。
別表第一の三、第一の四
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
資格外活動の許可を受けることが必要(入管法第19条第1項第2号・第2項)。
その在留資格により活動できない活動をして報酬やその他の収入を得た場合、不法就労となります。
資格外の活動のほか、旅券や上陸許可なく本邦に上陸した者や在留資格を失った者、在留期間を経過した者等、在留資格が無い者が活動をして報酬やその他の収入を得た場合も不法就労となります。(出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第3の4号イ)。
不法就労助長罪
このような外国人に不法就労活動をさせた場合、不法就労助長罪となります。
入管法では、次のいずれかに該当する者について、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と定めています(入管法第73条の2第1項)。
① 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
② 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
③ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
この行為をした者は、次のいずれかに該当することを知らないことを理由として処罰を免れることはできません。ただし、知らなかったことについて過失がなかったときは、処罰されません(入管法第73条の2第2項)。
① 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
② 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり許可(入管法第19条第2項)を受けていないこと。
③ 当該外国人が在留資格のない者(入管法第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4)であること
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関してこの罪を犯したときは、行為者だけでなく、その法人又は人に対しても、300万円以下の罰金刑が科されます(入管法第76条の2)。
事業主は、外国人の氏名や在留資格、在留期間などの事項を、在留カードや旅券・在留資格証明書などにより確認しなければなりません(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第11条第1項)。こうしたことを怠っていると、知らなかったことについて過失がなかったとすることは困難になります。
まとめ
このように、不法就労者を雇うようなことをしてしまうと、採用担当者だけでなく企業自身も重い刑罰を科されることになります。不法就労をさせないことはもちろん、雇用の際に、外国人の在留資格などについてもしっかりと確認する必要があります。
外国人の雇用についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。